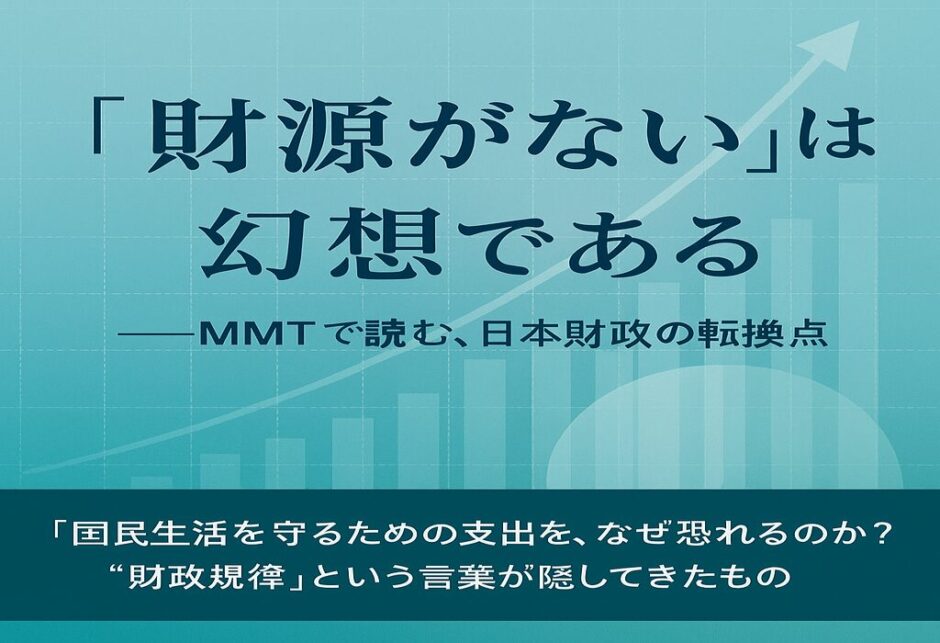846 05 20:00-21:00
本稿は、ロイター通信社による以下の記事に触発されて書き始めたものである。
マクロスコープ:身構える霞が関、「非常によくない方向」 参政・国民民主の躍進で「ロイター 鬼原民幸氏]
2025年7月22日午後 1:54 GMT+92025年7月22日更新さらに記事本文では、次のような内容で展開されている――
2025年参院選で、参政党と国民民主党が躍進したことに、霞が関(官僚機構)に警戒感が広がっている。両党は減税や積極財政を掲げる「積極財政派」であり、財務省などの財政再建を重視する省庁にとっては「非常によくない方向」と受け止められている、、、、
参院選で参政党や国民民主党が躍進し、霞が関がざわついている。なぜなら、これらの政党が掲げる「減税」や「積極財政」は、長年「財政再建」を信条としてきた財務省にとって、明確な異端だからである。
だが本当に問うべきは、「財政赤字が悪かどうか」ではなく、「その支出が社会にとって有効であるか」である。
MMT(現代貨幣理論)は、このような問いに正面から応える理論と実践の道を示唆している。本稿では、今後の日本が取るべき新しい財政運営の指針について、MMTの示唆する観点から具体的に提言する。
参議院選挙における参政党・国民民主党の躍進は、財政再建を至上命題としてきた日本の財政政策に対して、国民の新たな意思表示である。とりわけ若年層の支持が顕著であり、「財政赤字=悪」という従来の財務省的ロジックが通用しなくなっている現実が浮き彫りになった。ここにこそ、MMT(現代貨幣理論)を軸とした政策転換のチャンス、可能性がある。
財政運営の基準を「税収」から「インフレ率」へ
MMTは、通貨発行権を持つ政府にとって税収は支出の前提条件ではなく、インフレの調整手段であると位置づける。日本のように長らくデフレに悩まされ、賃金停滞と低成長に苦しむ国にとって、支出抑制によるバランス達成は逆効果である。支出判断の基準は「税収額」ではなく、「経済全体の需給バランス」=「インフレ率」であるべきである。
ジョブ・ギャランティ制度の導入
民間が吸収できない労働力に対して、政府が「最後の雇用主」となり、地域社会のニーズに応える形で公的雇用を保障する制度が求められる。これは単なる失業対策にとどまらず、地域インフラ整備や介護、教育、気候対策などと結びつくことにより、社会的課題の解決と所得安定を同時に実現する。結果として消費の底上げ、需要創出、地域の再生にもつながる。
地域主導型の準公共通貨の実験的導入
参政党が支持を得ている地方において、中央財政とは別に、地域限定通貨や「地域公共ポイント」的制度を導入し、未活用の労働力や資源を循環させる試みを支援すべきである。MMTが理論的に支持するこの方策は、地域経済の底上げと自治の強化を同時に達成するツールとなる。
税の再定義:財源確保から「インフレ調整と格差是正」へ
税は政府支出の財源ではない、というMMTの立場に立てば、税制の役割は主に「インフレ抑制」「所得再分配」にある。逆進性の強い消費税よりも、所得税・資産課税を強化しつつ、景気循環に応じて柔軟に税率を操作できる制度設計が必要である。減税と増税のタイミングを「物価」と「雇用」に基づいて判断することが重要である。
「財政規律」の再定義と制度的説明責任の明文化
「財政規律」という語が「赤字を出さない」ことと同義に扱われている現状は誤りである。むしろ「社会の持続可能性」「物価の安定」「雇用の全体最適」という三点を基準とし、それを国会や国民に定期的に報告・説明する制度的枠組みが不可欠である。財務省の独自判断に依存するブラックボックス的な財政運営から、国民参加型の開かれた政策運営へと転換せねばならない。
結論:恐れるべきは支出そのものではない
これからの時代に必要なのは、財政支出そのものを恐れる姿勢ではなく、「どこに・どのように支出するか」を誠実に吟味する設計思想である。日本は、自国通貨を発行できる主権国家である以上、「財源がないからできない」という説明は根拠を失っている。求められるのは、現代社会の課題に対し、通貨主権を活用して責任あるかたちで応える国家の姿である。古い殻を打ち破れ。
————————- ————————-
QAコーナー
Q 池上彰氏がテレビで語っていた「税金で足りない分を国債で補っている」は正しいか?
A テレビなどで池上彰氏が語っていたそのフレーズは、多くの人々にとって国家財政を理解する際の出発点となっているだろう。しかし、この説明は一見正しそうに聞こえつつも、多くの誤解を招く原因ともなるものである。現代の経済理論からは異なる視点も存在する。以下、その正確性と限界について考察する。
政府財政の構造:伝統的な説明
日本政府の歳出は、主に①税収、②その他の収入(印紙・財産収入など)、③国債発行という三本柱で成り立っている。一般的には、税収などで賄いきれない「赤字」分を国債で補っているという構図である。この意味で池上氏の説明は、財務省の公式資料や教科書的な理解と一致しており、形式的には正しい。
しかし…MMT(現代貨幣理論)から見るとどうか?
MMTでは、国家の財政運営をまったく異なる順序でとらえる。政府は自国通貨を発行する存在であり、まず支出によって通貨を供給し、その後に税金で一部を回収するという循環が基本構造である。したがって、「税金が足りないから国債で補う」という表現は、国家が通貨を発行できるという根本的な事実を覆い隠す結果になりかねない。
誤解されがちな国家財政の3つのポイント
1つ目は、政府は家計と違い「お金を稼ぐ」必要がないという点である。通貨の発行権を持つ国が、家計のように「足りないから借りる」という発想をしていたら、本質を見誤る。2つ目は、国債は将来世代へのツケという常套句の誤りである。むしろ国債は、将来世代が受け取る利息収入として国民経済に還流する。3つ目は、税金が足りなければ破綻するという誤解である。日本のように自国通貨で国債を発行する国は、デフォルト(債務不履行)に陥ることは理論的にあり得ない。
では、なぜこのような説明がまかり通るのか?
背景には「財政規律」や「均衡財政」への信仰がある。政府の借金=悪という観念は、戦後のドイツ的なトラウマや、家計簿感覚による誤認が根強く作用している。また、財務官僚による情報発信が強く影響している可能性も否めない。
結論:説明は形式的には正しいが、本質を見誤る危うさがある
池上氏の説明は、一般的な理解としては有用であるが、それが唯一の正解と捉えると危険である。国家財政の本質を深く知るには、MMT的な発想――つまり「政府は通貨発行主体であり、まず支出から経済を回している」という視点を持つ必要がある。これが、コペルニクス的な発想と言われる所以である。が、正しいということは比較的理解されやすいのではないだろうか。そして、税金と国債の関係を見直すことで、これまでとは異なる政策の可能性も見えてくるだろう。
■ 出典・参考文献
1. 池上彰氏の発言について
- テレビ東京『池上彰のニュースそうだったのか!!』(複数回放送)
※直接の文献化はされていないが、「政府の予算は税金で足りない分を国債で補う」との趣旨はたびたび語られている。 - 著書:池上彰『そうだったのか! 現代史』(集英社文庫、2002年)
※国の借金に関する基礎的説明が含まれている。
2. 財務省による公式説明
- 財務省『令和6年度予算のポイント』
https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2024/seifuyosan/index.htm
※「歳入不足を公債で補っている」という構造が明記されている。
3. MMT(現代貨幣理論)の立場
- ステファニー・ケルトン著『財政赤字の神話』(原題:The Deficit Myth、早川書房、2021年)
※「税は支出の前提ではなく、インフレ調整や格差是正の手段」と明言。MMTの中心的理論書。 - 中野剛志『富国と強兵』(東洋経済新報社、2016年)
※日本語でMMTに近い立場から財政観を論じている。財務省的見解への批判も展開。 - 三橋貴明『MMTが日本を救う』(ビジネス社、2019年)
※通俗的だが、一般向けにMMTを解説しており、国債=借金という考え方を疑う。
4. 国会や識者による議論・資料
- 衆議院調査局『国債に関する基礎資料集』(2023年版など)
- 日本銀行『国債の保有と貨幣供給に関する考察』
https://www.boj.or.jp/research/wps_rev/rev_2023/rev23e05.htm/