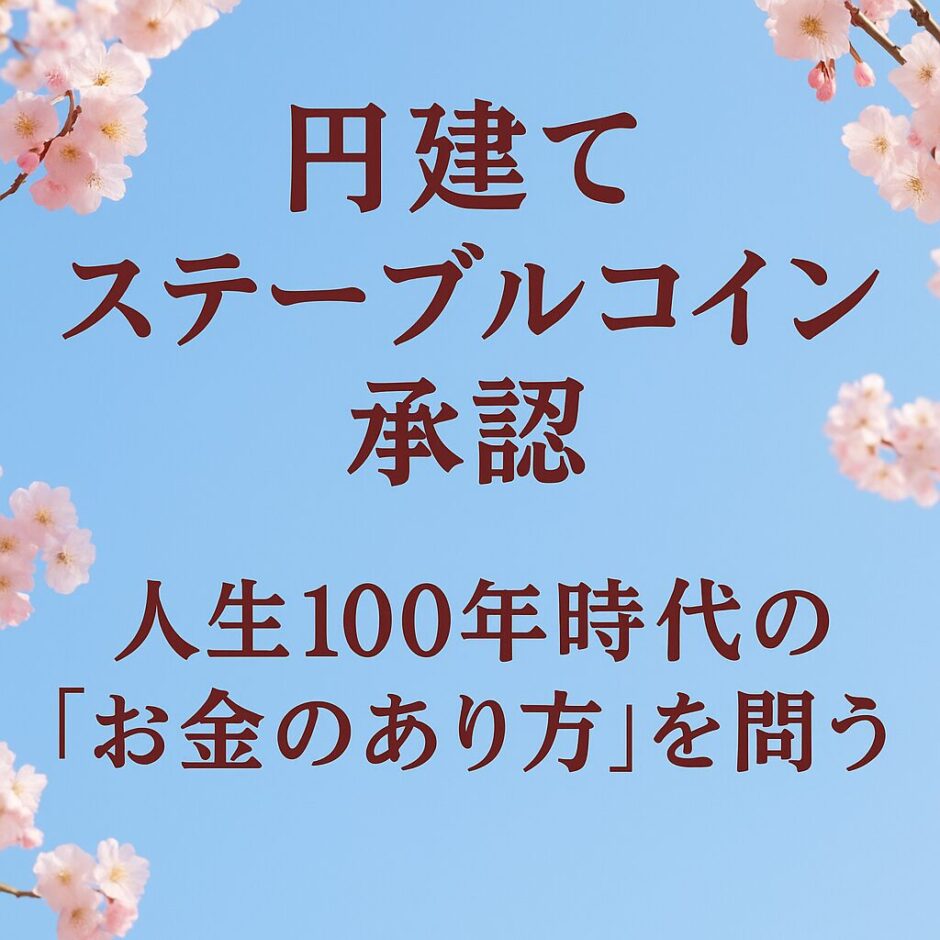875 03 04
金融庁が今秋にも、日本初となる円建てステーブルコイン「JPYC」を承認する。これは単なる金融ニュースにとどまらず、私たちの暮らし方や生き方に直結する動きである。
円に連動するデジタル通貨が国内外で使えるようになれば、留学生への仕送りや国際送金の手数料は格段に下がり、時間も短縮される。人生100年時代、海外とつながりながら暮らす人が増えるなかで、安心して「円」を持ち運びできる環境が整うことは心強い。
また、ブロックチェーン技術を基盤にした決済手段は、銀行口座を持たない人にも広がる可能性を秘めている。高齢者にとっても、紙幣や通帳に縛られずに「電子財布」で資産を管理する時代が現実となりつつある。老後の生活を支えるお金の形が、従来の「現金」から「デジタル円」へと移り変わるのだ。
一方で、金融の仕組みが変わるということは、リスクの形も変わるということでもある。資産運用や送金の自由度が高まる反面、セキュリティや制度設計が不十分なら、高齢者や一般生活者がトラブルに巻き込まれる懸念も残る。ここには、社会全体での知識普及や利用環境整備が欠かせない。
結局のところ、円建てステーブルコインは「お金の老化」を防ぐ一歩とも言える。紙幣や硬貨の役割が弱まりつつある時代に、新しい形の円を受け入れることは、長寿社会を生き抜くための知恵の一つになるのではないか。
老活世代にとっての問いはこうだ。
「自分のお金を次の世代にどう残すのか。そして、どう使うのか。」
円のデジタル化は、その答えを探す新たな舞台を提供している。