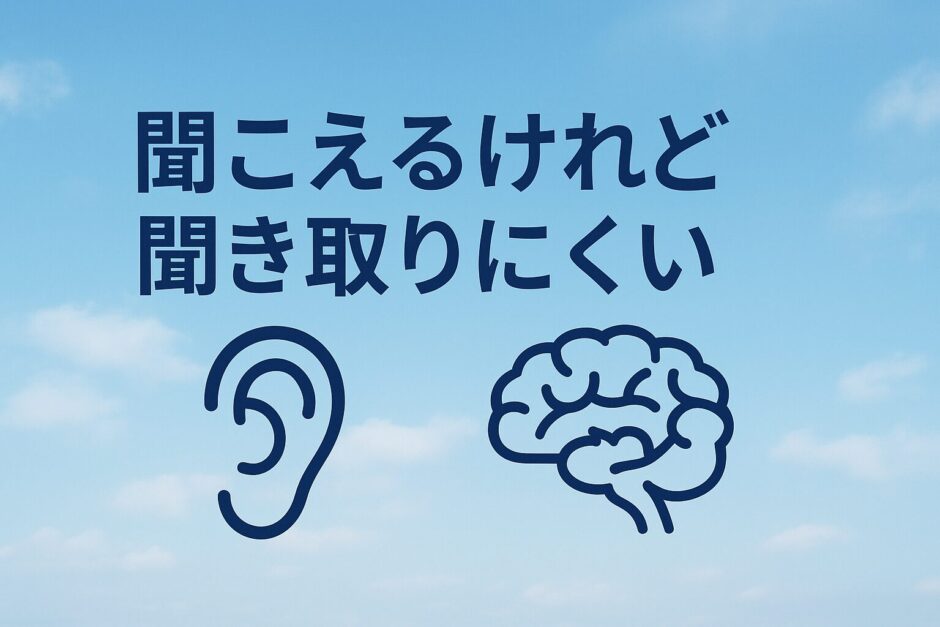920 04 07 09
また新しい病気が生まれたのか?生まれたというのは語弊があるが、新しい病気の分野が生じたようである。実際、私自身が思い当たるので、深掘りしてみたくなった。
2025/10/03 起草
音は聞こえているのに、言葉として理解しにくい――
「聞き取り困難症(LiD)」という症状が注目されている。
従来の「聴覚情報処理障害(APD)」を含む新しい概念であり、生活や仕事に支障をきたす人も少なくないという。
本記事では、その症状や診断、当事者と周囲の工夫、そして支援の現状を整理する。
聞き取り困難症(LiD)とは
音は聞こえるのに言葉として理解しにくい症状である。
以前は「聴覚情報処理障害(APD)」と呼ばれていたというが、注意・記憶・言語能力など認知機能の関与も明らかになり、現在はAPDを含む広い概念としてLiDとされる。
聴力検査では正常と出ることが多いが、言葉として理解する「リスニング」が困難になる。自分の思わぬ隠れた症状が表に出てきた感じである。
主な症状・特徴
・✍️聞き返しや聞き間違いが多い
・✍️長話しで集中し続けるのが困難
・複数人での会話で誰が話しているのかわかりづらい
・雑音の多い環境で会話が聞き取りにくい。
✍️概ね私の症状はそれに近い。私の場合、多勢の話中で他の人が理解しているのに、私には相手が何を話しているのか、聞き分けるのが難しいという症状である。聴覚の検査では何の問題もない。
その当時は、他の人もそうだろうと推測していたが、他人はきちんと聞き分けていた。自分が聞こえないはずはない、という先入観があったのだが、しかし他の人の様子を見ていると私が聞き取れないことを周囲の人が識別できていたように思う。何回かそんな時があった。おかしいな、程度に思っていたのであるが、今日、そうした事例が取り上げられていたので、じっくり調べてみようという気になった。
<memo>これまでの対応策メモ ‖ 人の話を所々取りこぼすので、その間は推量して補填し、内容がはっきりしない時はメモしておき、確認するようにしていた。あとで辻褄が合わないような場合のためである。次第にメモ魔となったのはいいが、そうなるとメモに頼りがちになる。これが時には二次弊害を生み出す</memo>
・国内で100人に1人が該当とされるが、潜在的にはもっと多い可能性がある。
診断と相談
・まずは耳鼻科で聴力検査を受けることが勧められる。 ‖ 済。むしろ、年齢の割に聴覚は良い、という結果である。
・LiDを掲げる精神科や心療内科もあるが、隠れた難聴が発見される場合もある
・2024年に「LiD/APD 診断と支援の手引き」が国内初公表
当事者の工夫
・静かな場所で1対1の会話を選ぶ
・補聴援助システム(マイクと受信機)、音声文字変換アプリを活用
・聴覚過敏にはノイズキャンセリングイヤホンが有効な場合もある。✍️ノイズキャンセルで効果を確認した。
周囲の配慮
・名前を呼んで注意を引いてから会話を始める
・大きな声でゆっくり、はっきり話す
・電話対応などは他の人が担当する
・コピー機や空調の少ない静かな席に配置する
・口頭指示は簡潔にし、重要事項は文字でも伝える(私は文章にして補っているが、高齢者では嫌がる人が多い)。
・会議では発言がかぶらないように進行する
今後の課題と支援の広がり
・診断できる医療機関は増えているが、個別支援機関はまだ少ない
・筑波大学の小渕教授がオンライン支援機関「Listening Support」を設立
・多様な聞き取りの困難に寄り添った支援拡大を目指している
まとめ
LiDは耳そのものに異常がなくても、生活や人間関係に大きな影響を与える「見えにくい障害」である。本人の工夫と周囲の理解・配慮があって初めて、困難は軽減される。社会の中での認知度を高め、支援のネットワークを広げていくことが今後の課題といえる。✍️私も聴力を疑われて耳鼻科で精密検査してもらったところ、全く問題ないという判定だった。
後日、新しい情報があれば追加する。
2025/10/3 日経新聞メルマガを参考に調査