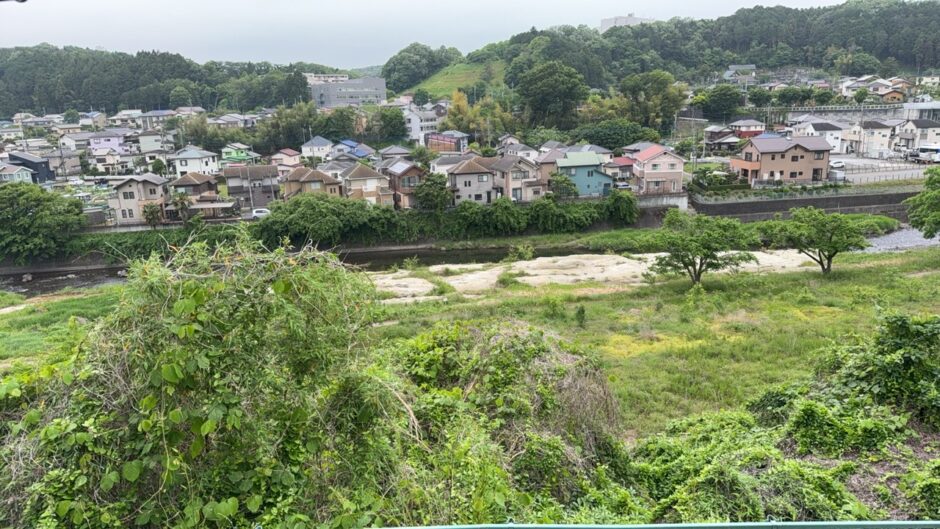770 10 8:00-9:00 v1.01
6:00-7:00 モーニングタイム
猫が毛玉を吐き出していた。知らずに踏みつけ危うく転ぶところであった。が、最近は家の中で歩く時は急がないことにしている。これが幸いして転ばないで済んだ。「なにがあっても、のらりくらり」これを新たな日常訓に掲げよう。

#国際関係
ロシアとウクライナが「数日内に文書で停戦案」 ルビオ米国務長官
【日経電子版ニュース要約】
米国のルビオ国務長官は5月18日、ロシアとウクライナが16日に行った直接協議において、「数日内に正式な停戦案を文書で提示する」ことで合意したと明らかにした。
現時点で詳細な内容は明かされていないが、戦闘が激化する中での合意は、国際社会にとって大きな意味を持つ。
👉視点
エネルギーや食料価格への影響が続く中、もし本当に停戦が実現すれば、日本の経済にもポジティブな影響が出てくる可能性がある。
[関連記事]バンス米副大統領、ゼレンスキー氏と停戦巡り協議 2月の口論以来
[関連記事]ゼレンスキー氏、ローマ教皇レオ14世と面会 「戦争終結に役割」期待
バイデン前米大統領が前立腺がん 骨に転移と公表[出所 日経電子版]
👉コメント
バイデン大統領は排尿障害を訴えて受診し、前立腺がんと診断された。すでに骨への転移が確認されており、悪性度はグリソンスコアで9(1〜10)とされ、進行度としては高い分類に入る。一般的に前立腺がんは進行が遅く、5年生存率が高いが、今回のように転移を伴うケースでは治療も難しくなる傾向がある。今後の経過と対応が注目される。聞くところによると、骨転移は痛みが強いと聞く。最高の医療を受けて早期に治癒することを祈念するのみである。
関税戦争の背景にドル防衛 プラザ合意40年、危険な賭け
[出所 日経電子版]
「プラザ合意2.0」。先進国が協調してドル高を是正した1985年9月のプラザ合意になぞらえ、通貨や通商の秩序を再構築しようという機運がトランプ米政権にくすぶっている。基軸通貨の重みと恩恵は複雑に絡み合い、米国の不満は世界に向かう。40年前よりはるかにグローバル化した世界で再現する「米国vs.世界」の構図。その先に見えてくるのは基軸なき世界なのか。
👉 【要約】
この記事は、1985年の「プラザ合意」から40年が経ち、現在の米国が再び通貨・貿易の見直しを通じてドル高の是正を図ろうとしている背景を分析している。
特に、トランプ前政権の「米国第一」政策が通商摩擦を再燃させ、「プラザ合意2.0」ともいえる新たな通商再編を志向している可能性を指摘。
だが、40年前と違い、今は経済のグローバル化が進み、各国の利害がより複雑化しており、協調的な合意は難しい。その結果、ドルの基軸通貨としての立場が揺らぎ、最終的には「基軸なき世界」に移行する危険性がある、と警鐘を鳴らしている。
👉 コメント
「プラザ合意2.0」という表現が示すように、ドル高是正をめぐる力学は40年前と似て非なる構図だ。当時のようにG5(*1)が協調して為替を調整する余地は乏しく、むしろ米国の単独行動が際立つ。「関税戦争」の裏には、基軸通貨ドルの覇権を維持したい米国の焦燥が透けて見える。だが、グローバル経済が多極化する中で、各国は米ドル依存からの脱却も模索しており、「基軸なき世界」への移行が現実味を帯びてきた。かつての合意に再現性はあるのか?歴史の教訓が試されている。
(*1)当時のG5
1985年のプラザ合意に参加した当時のG5の国
1. アメリカ合衆国 通貨は💲
2. 日本 同円
3. 西ドイツ ‖ 当時は東西に分裂 同マルク
4. イギリス 同ポンド
5. フランス 同フラン
この5カ国の財務大臣・中央銀行総裁がニューヨークのプラザホテルに集まり、ドル高の是正(円高・マルク高誘導)に協調介入することを決定した。
1985年の世界情勢は、冷戦の最終局面に差し掛かりつつある時代であり、政治・経済・技術の各分野で大きな転換点にありました。以下に、主要な動向を分野別に整理します。
⸻
【1. 国際政治:冷戦構造の変化の兆し】
• 米ソ冷戦の最中
東西対立は依然として継続していたが、ソ連でゴルバチョフ書記長が登場(1985年3月)し、のちのペレストロイカ(改革)やグラスノスチ(情報公開)の始まりとなる。
• 米国:レーガン大統領の「強いアメリカ」政策
「スターウォーズ計画(SDI)」など軍拡路線を継続。反共産主義の強硬姿勢を取りつつも、ゴルバチョフとの接触も始まる。
• 欧州:西ドイツが経済的主導権を強める
西側陣営の中で、欧州統合に向けた動きも静かに進行。
• アジア:日本の経済台頭と中国の改革開放
日本は世界第2位の経済大国として注目され、米国との貿易摩擦(特に自動車・半導体)が激化。中国では鄧小平の指導下で「改革開放」が本格化していた。
⸻
【2. 経済:通貨問題とグローバル化の序章】
• ドル高が深刻化(1980年代前半)
米国の金利引き上げにより、ドルが異常に高騰し、米製品が国際競争力を失う。これが貿易赤字を拡大させ、日本・西ドイツとの摩擦を激化させた。
• プラザ合意(1985年9月)
上記の背景から、ドル高を是正するためにG5が協調介入を実施し、円高・マルク高誘導が行われた。
• 日本のバブル経済の萌芽
プラザ合意後の急速な円高を受けて、日銀は金融緩和を強化。その結果、日本国内では資産バブルが加速しはじめる。
⸻
【3. 社会・技術:ポスト産業社会の兆し】
• パーソナルコンピュータの普及期
米アップルやIBMが個人向けコンピュータを販売し始め、情報化社会の幕開けを感じさせる時期だった。
• 音楽・文化面ではMTV(*1)が世界を席巻
マイケル・ジャクソン、マドンナなどの登場により、グローバルポップカルチャーが拡大。
• インターネットは未発達、冷戦技術としての軍事通信網の時代
注記(*1)MTV ミュージックビデオを24時間放送するアメリカのケーブルテレビ局として、1981年に開局した。
📍 9:00-ウォーキング再開
→atミスタードーナッツ店 / 過去データの整理
📍 11:00- 帰宅
――
→ 午後のウォーキング
歩くたび 休む理由を 探しけり
歩きまた ひと息ついて 春の暮
📍 -19:00 atマクドナルド店
📍 20:00- 帰宅 11400歩
📍 22:00 The day is drawing to a close.