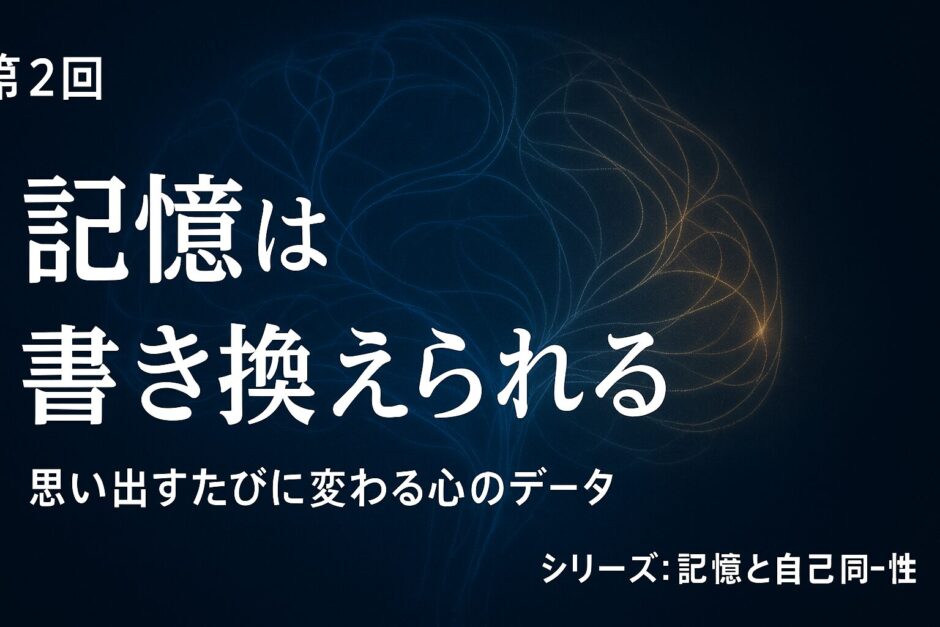7950 09
【第2回】 記憶は書き換えられる
― 思い出すたびに変わる心のデータ

記憶とは、固定された映像のようなものではない。
私たちは「記憶=過去の正確な保存」と思いがちであるが、実際の脳内では、思い出すたびに記憶が少しずつ形を変えている。この現象は、神経科学で再固定化と呼ばれる。
⸻
思い出すたびに、記憶は“再編集”される。
かつては、記憶は脳に安定して保存された後は変化しないと考えられていた。
しかし、21世紀に入ってからの研究で、「思い出す」という行為そのものが、記憶を一時的に不安定化させ、その後に再び保存し直すプロセスがあることがわかってきた。
まるで古い日記を開き、そこに新しい注釈を書き加えるように、私たちは過去を少しずつ“書き換えながら”生きているのである。
⸻
記憶の再固定化
神経回路の可塑性が生む柔軟さ。思い出すたびに記憶が更新される背景には、脳のシナプス可塑性と呼ばれる仕組みがある。
神経細胞同士の結合は、使われるたびにわずかに強くなったり、弱くなったりする。その変化の積み重ねが、私たちの学びや経験の“形”を作る。
たとえば、ある出来事を思い出すとき、その時の感情や状況が新しい情報として上書きされる。結果として、同じ記憶でも、時を経て「感じ方」が変わる。
これが人間らしい記憶の柔軟性であり、記憶が単なる記録ではなく、生きた情報であるゆえんである。
⸻
トラウマ治療にも応用される「記憶の書き換え」
この再固定化の仕組みは、近年、心理療法やPTSD治療にも応用されつつある。過去の辛い記憶を想起した状態で、安全な環境下で新しい感情や刺激を与えると、記憶の“情動部分”が書き換えられ、苦痛が軽減されることがある。つまり、記憶の内容は変えられなくても、それに付随する感情を更新することができる。だからこそ過去の失敗も生きてくる。傷も時と共に癒やされるのである。
⸻
人は、過去を修正しながら生きている
思い出すことは、自分の過去を“再編集”し、現在を生きるのにふさわしい形へと更新する行為である。人はその繰り返しの中で、「今の自分」を形成し続けている。
ゆえに、原則的に過去の出来事は変えられないが、過去の意味はいつでも変えられる。それが、記憶の持つもう一つの救いであり、再生の力である。
⸻
まとめ
- 記憶は固定されたものではなく、思い出すたびに再構築される。
- 記憶は思い出すたびに「再固定化」することにより、古い記憶が新しい感情や情報で更新される。
- トラウマ治療などにも応用されている科学的現象である。
- 記憶は“書き換えられる過去”として、現在を生きる力となる仕組みなのである。
⸻
付記:記憶の哲学的意味
私たちは過去を「思い出す」ことで、自分を確かめている。だが、その記憶が変化し続けているということは、“私という存在”もまた常に更新されていることになり、記憶が流動的であるがゆえに、人は変わり、成長できる。「男子、三日会わざれば刮目して見よ」である。変化の中に、生命の本質がある。2025/10/29
【メモ】参考文献は最終回の後尾に一括掲載予定。