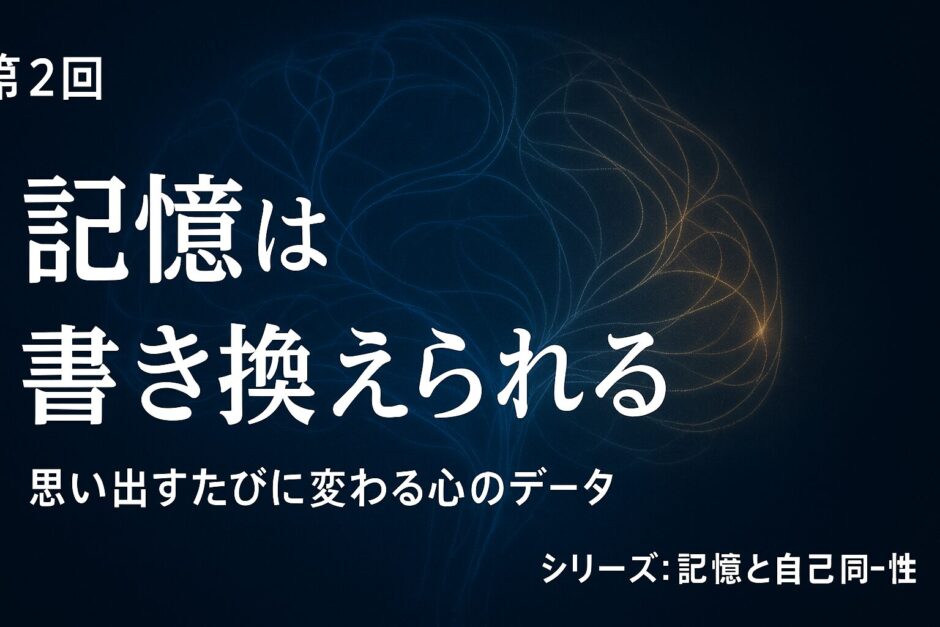952 00
第3回 記憶と自己 ― 私はどこまで「同じ人間」なのか

昨日の自分と、今日の自分は、果たして同じ人間なのか?
私たちは日々変化している。体の細胞も入れ替わり、思考も感情も少しずつ違っていく。それでも、私は「自分が自分である」と感じ続けている。
この感覚の源が、記憶による自己の連続性である。記憶が「私」を形づくる。自分が誰であるかを知るためには、「過去の記憶」が不可欠である。
幼い日の体験、出会い、失敗、喜び――それらの積み重ねが「私」という生涯の物語を形づくってゆく。
もしそれらの記憶を失えば、人格は根底から崩れてゆく。記憶とは、単なる情報の保存ではなく、自分という物語の骨組みなのである。
記憶喪失と自己喪失。
事故や病気で記憶を失った人が「自分が誰か分からない」と語るのは偶然ではない。たとえ身体はそこにあっても、過去との連続が断たれたとき、人は「私」という実感を見失う。
哲学者ジョン・ロック(*1)は著作で、「人間の同一性とは、意識の連続にある」と述べた。
つまり、記憶がある限り、私は同じ“私”であり続けるという考えである。
しかし、記憶は変化する。
第2回で述べたように、記憶は固定されたデータではない。思い出すたびに再構築され、時とともに色を変える。
では、記憶が変わるたびに「私」も変わっているのだろうか。
答えは、“変わりながら続いている”である。
川の水が常に入れ替わっていても「同じ川」と呼ぶように、私たちの意識もまた流動的でありながら、全体としての形を保っている。よく知られている鴨長明の方丈記に『ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは――』と書かれているが、まさに人も同じように見えて中身は変化しているのである。
AI時代に問われる「自己の境界」
近年、AIやデジタルコピーによって、人の記憶や人格をデータ化できる時代が近づいている。
もし自分の記憶と性格をそっくりそのまま移したAIがあったとして、その存在は「私」と呼べるのだろうか。
データとしての記憶は再現できても、その背後にある「感情・意識・体験としての私」は複製できない。人間とは単なる情報ではなく、変化の中で生き続ける存在だからである。
老いとともに変わる自己。
年齢を重ねるにつれて、記憶の一部は薄れ、感情の反応も穏やかになる。忘却と記憶の選別を通じて、人は自分にとって大切なものを選び直し、物語を再編集している。
老いとは、記憶による自己の再設計の時期なのかもしれない。
今、改めてそれでいいでのではないと思う。過去を辿れば誰しも幾度となく失敗を重ねているはずである。それで立ち直れなくなって旅立つ、というのではあまりに酷ではないか、と思う。年老いて、過去をすっかり忘れて幸せそうな顔になって旅立てるなら、それでいい。おそらく、死に苦しみが伴うとすれば、現世の苦しみを忘れさせる自然の営みかもしれない。そんな事を思い浮かべた。
まとめ
- 記憶は自己の連続性を支える「物語の糸」である。
- 記憶が失われると、自己もまた揺らぐ。
- 記憶は変化し続けるが、その流れの中に「私」が存在する。
- 老いとは、記憶の再構成を通じた“自己の再創造”である。
付記:記憶と魂の境界
もし記憶がすべて失われても、私たちはまだ「生きている」と言えるのだろうか。記憶を超えてなお存在する“意識の光”があるとするなら、それこそが魂の本質なのかもしれない。記憶と自己――この二つの関係は、科学を超え、哲学と宗教の領域にまでつながっている。
————————-
[注記*](*1)ジョン・ロック
【参考】
- 17世紀イギリス、清教徒革命(ピューリタン革命)や名誉革命の時代を生きた
- 彼の主な思想領域:
- 政治思想:自然権・社会契約論の提唱者。人は生まれながらにして「生命・自由・財産」の権利を持ち、政府はそれを守るために存在するとした。専制政治を否定し、抵抗権(革命権)を認めた。→ 名著『統治二論(市民政府二論)』において明示
- 認識論:経験論の祖。「人間の心は白紙(タブラ・ラサ)で生まれ、経験によって知識を得る」と主張した。→ 主著『人間知性論』で展開
- 教育論:「健全な身体に健全な精神」を重視し、実践的・道徳的な教育を重んじた→ 著書『教育に関する考察』
▼当時の三大思想家
ジョン・ロック、モンテスキュー、ルソー
ロックの思想は、後のフランス啓蒙思想やアメリカ独立宣言にも強い影響を与え、今日まで「近代自由主義の父」と呼ばれている。
251030初稿